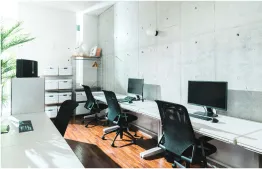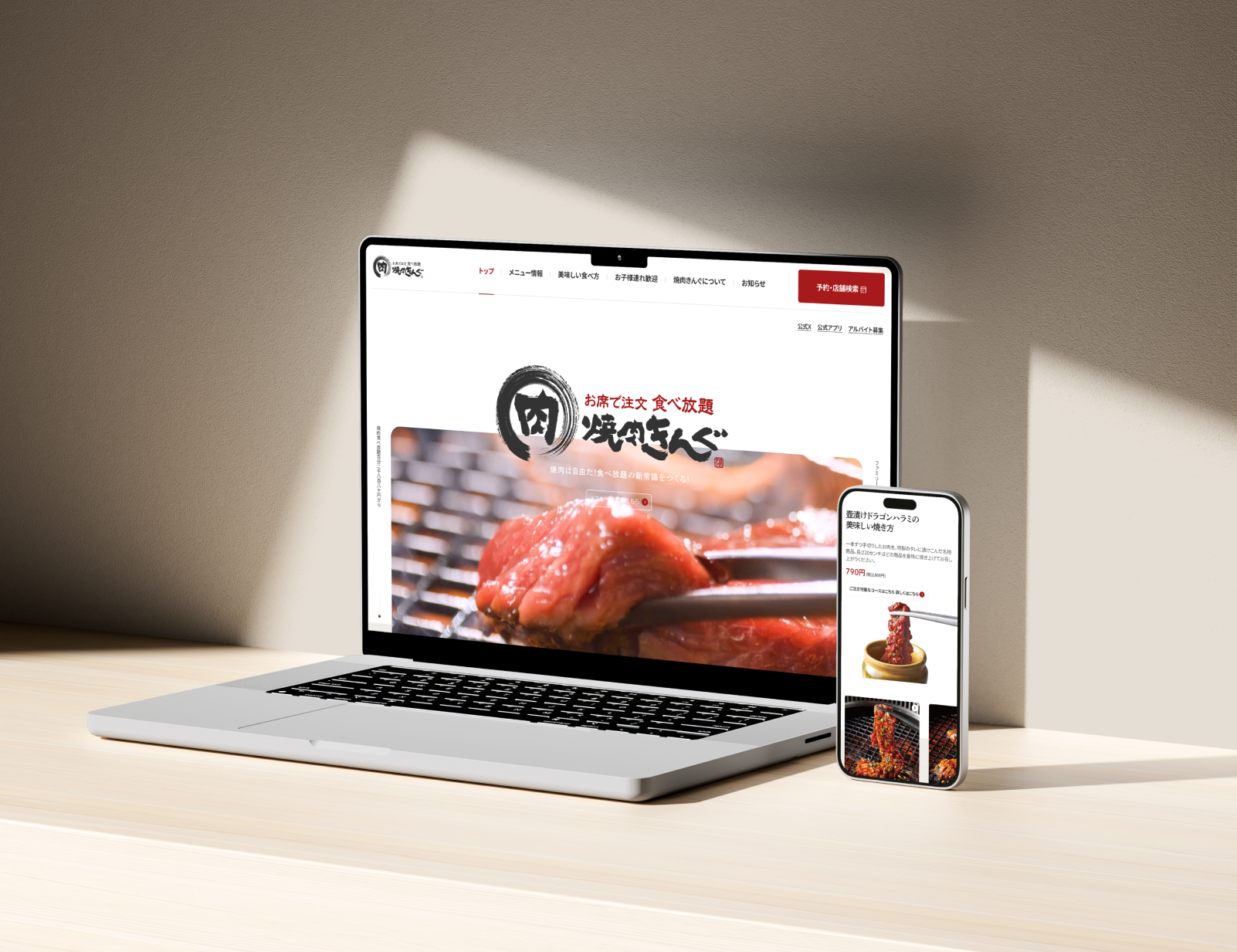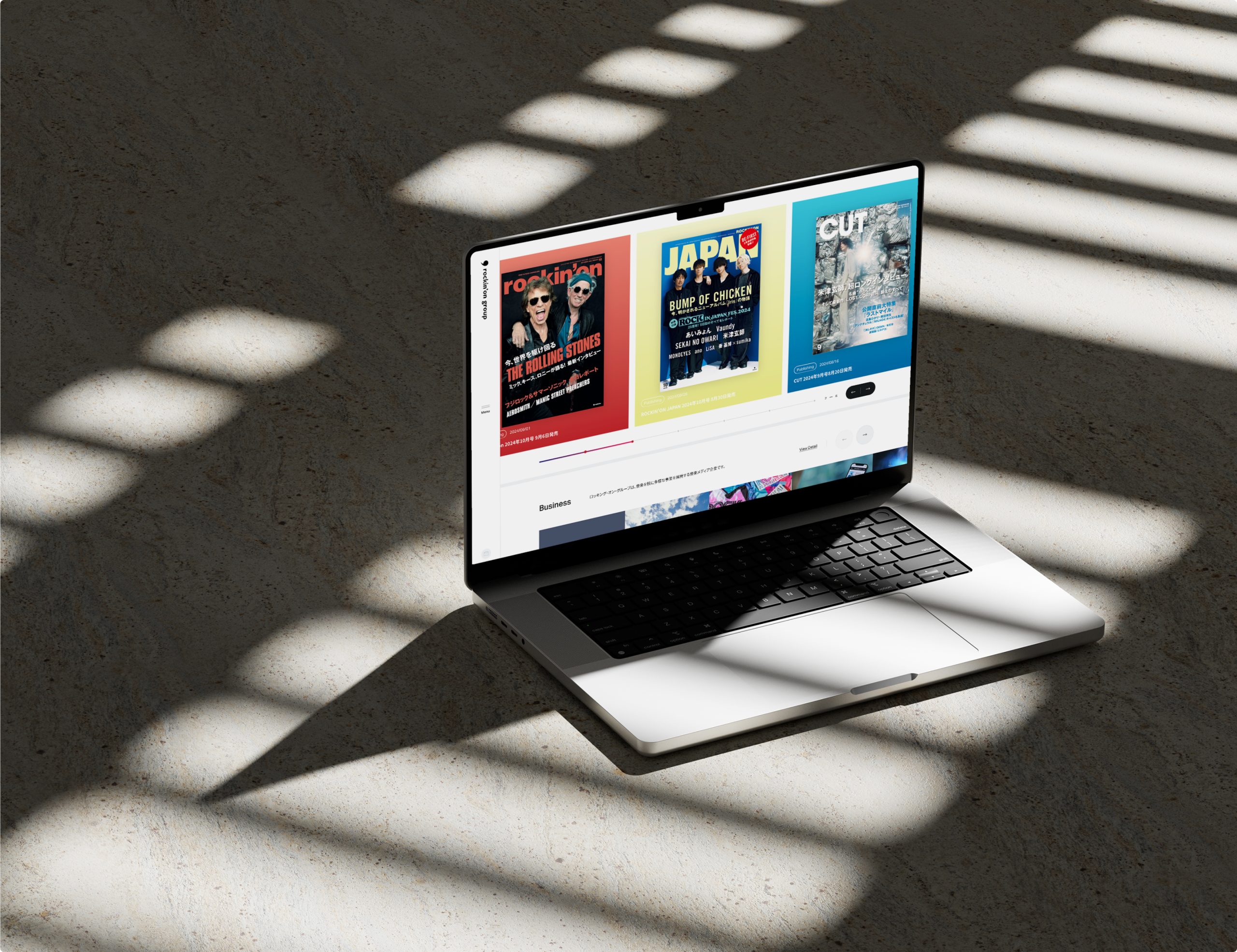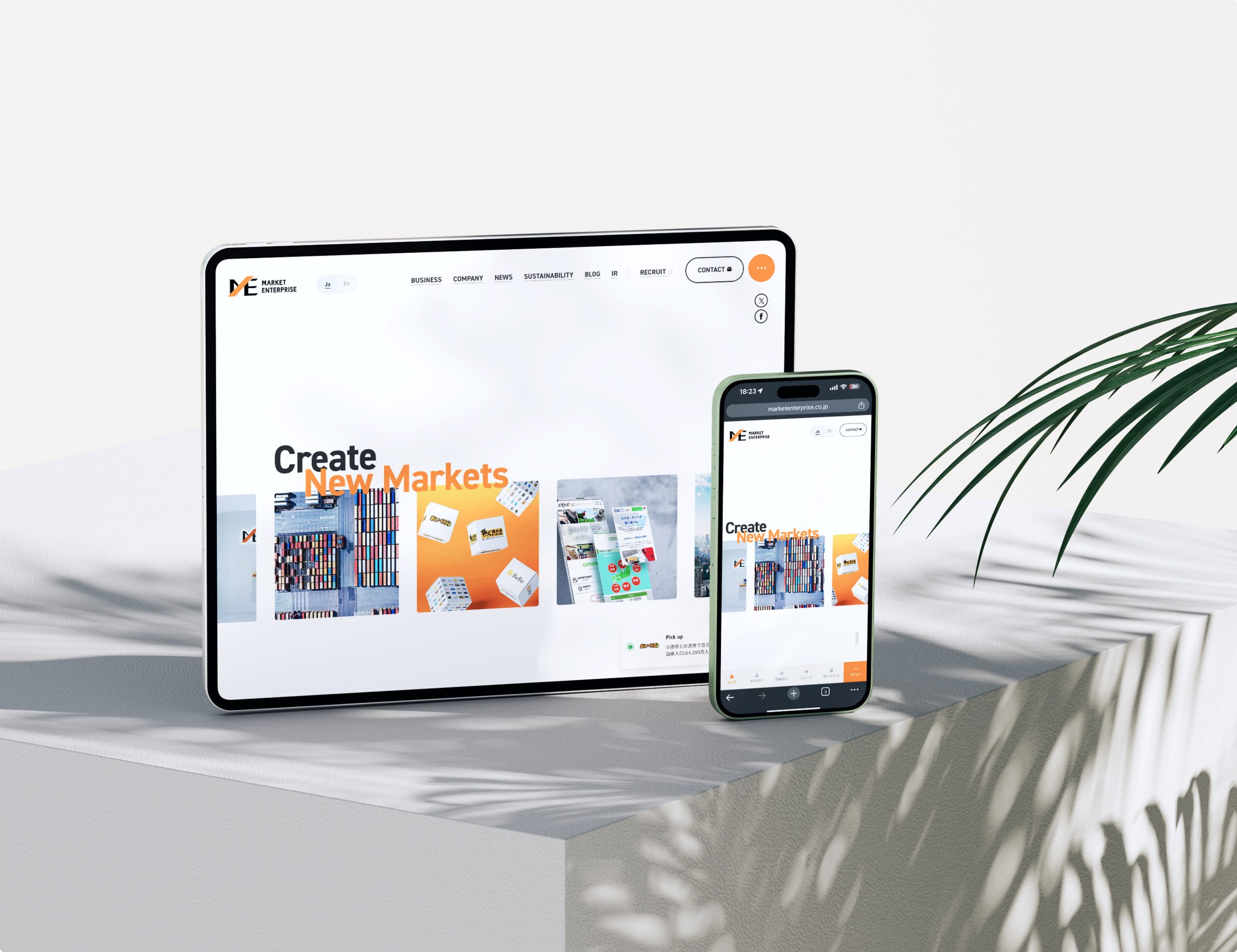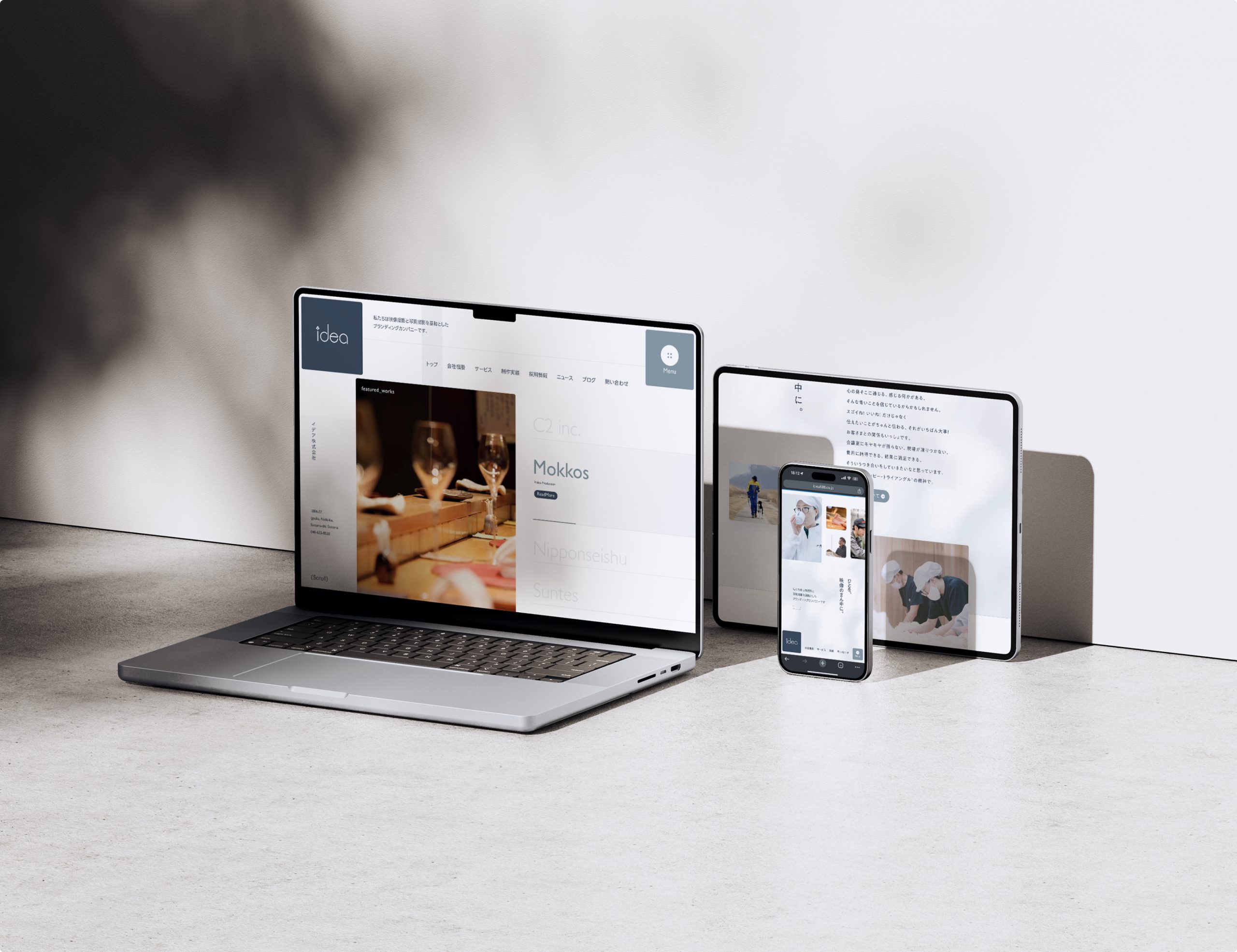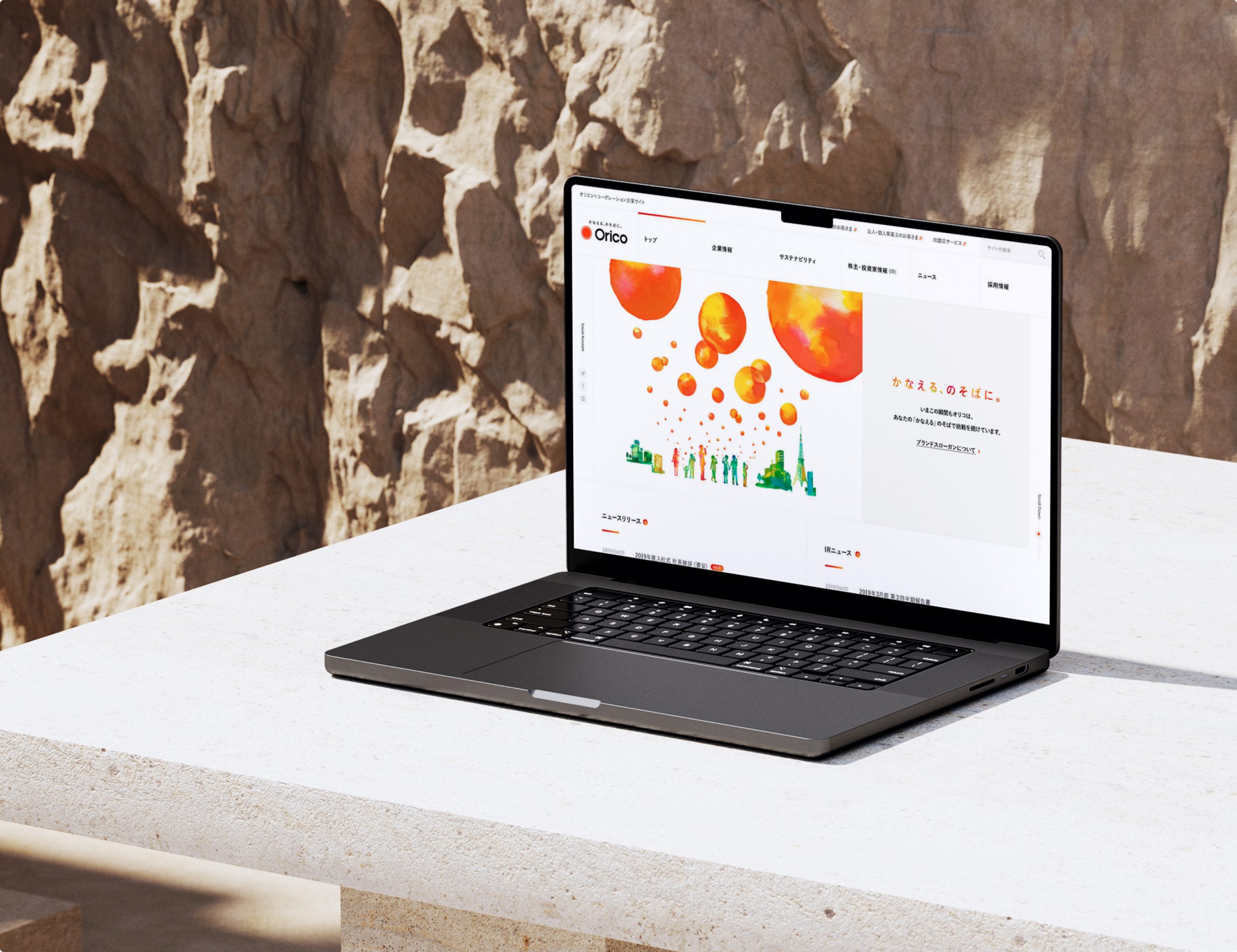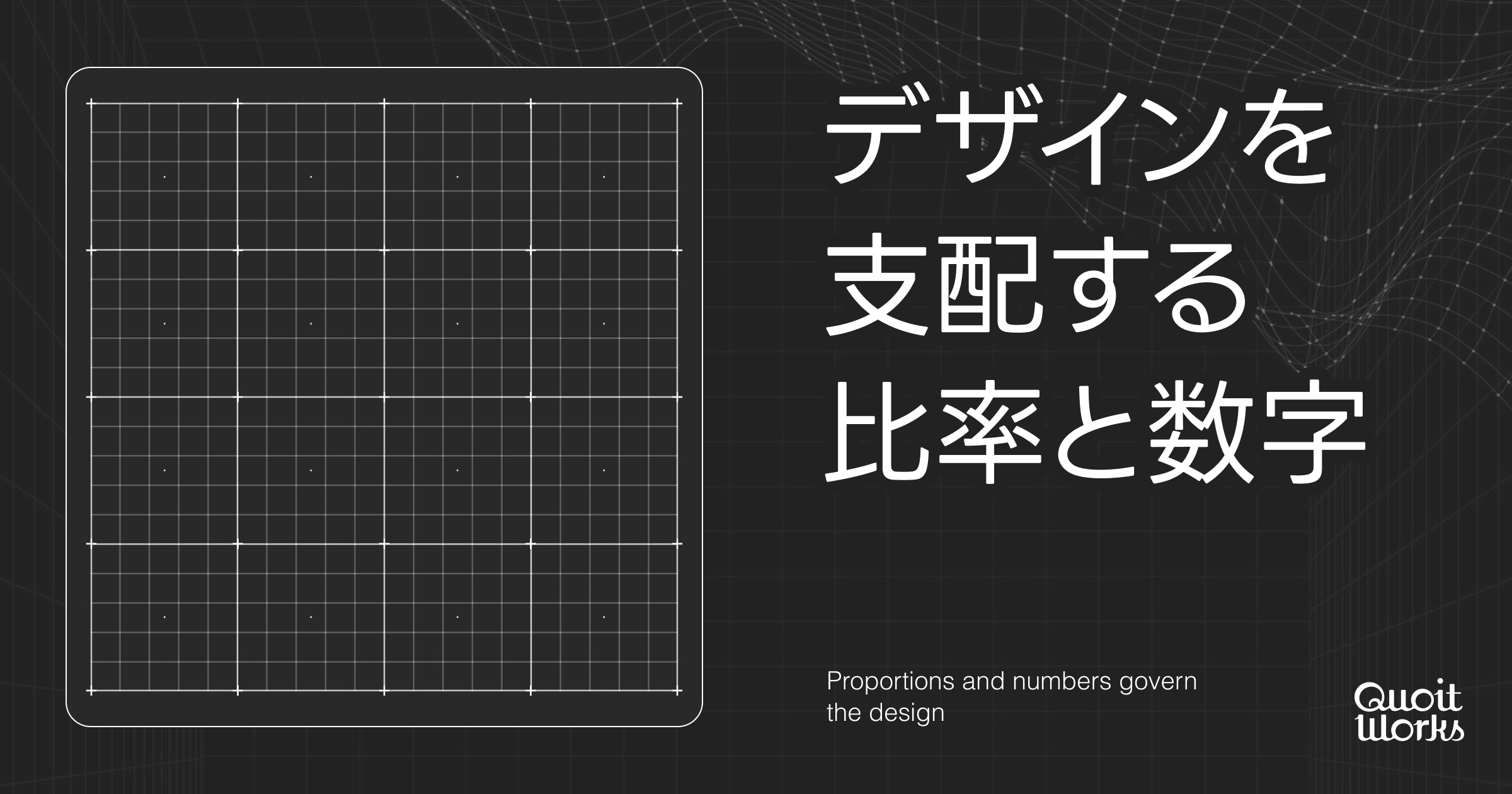サカナクション・山口一郎さんの深夜配信で、一つのサプライズが起きた。母子家庭で育ったミズキという女性が、母親に内緒でライブのチケットを取り、配信を通じてそれを伝えた。山口一郎さんはその話を聞いて「自分のことばっか考えてた」と気づく。そして「我々だけのドキュメンタリーじゃない。見に来てる人たちのドキュメンタリーでもある」と語った。
この言葉を聞いて、受託デザインの仕事も同じ構造に見えたという話です。
母子家庭のミズキのサプライズ
サカナクションの山口一郎さんが、深夜の配信でリスナーに電話をかけた。ミズキという女性からのメッセージに応える形だった。
「まだ誰にも言っていない秘密があります。一番に聞かせたいのが、今隣の部屋で一郎さんの配信を聴いている母です」
ミズキは自分の部屋から山口一郎さんと電話している。そしてお母さんは隣の部屋で、いつも通り配信を見ている。お母さんは娘が今、配信の中で山口さんと話していることに気づいていない。
電話の向こうでミズキは語った。母子家庭で育ったこと。母がサカナクションのライブに行きたがっていたけど、チケット代が負担でなかなか行けなかったこと。そして自分がこっそりチケットを取ったこと。
「明後日5月18日にある仙台のサカナクションのライブのチケット、2枚取ったので、お母さん連れて参戦させていただきます」
山口一郎さんが「お母さん見て!」と呼びかけると、隣の部屋で配信を見ていた母親が応答する。サプライズは成功した。
プロでも陥る「自分のことばかり」
山口一郎さんは電話を切った後、こう語った。
※5:50以降が必見です
「ライブで我々が知らないうちに、このライブに来るためにいろんなドラマが多分あるんだよ。水希のようなドラマが。物語があるんだよ。俺の物語なんてちっぽけだよ」
そして続けた。
「思い出したわ、俺はやっぱり図に乗ってた。自分のことばっか考えてた、病気になってから。我々だけのドキュメンタリーじゃないんだよな。見に来てる人たちのドキュメンタリーでもあるんだよな、ライブって。だから一個一個、その時の全力のベストライブをやっぱり見せてかなきゃいけねえんだな。命かけてやるわ」
ここで印象的なのは、山口一郎さんほどのプロフェッショナルが「図に乗ってた」「自分のことばっか考えてた」と言っていることにあると思っている。
観客のことを考えるのは、パフォーマーとして当たり前のことのはず。でも当たり前のことが、できなくなる。
山口一郎さんはうつ病で療養中だった。自分の体調と向き合う日々。自分との戦い。それは必要なことだったけれど、「そこに集中しすぎてて、なんか見落としそう、見落としかけてたものを拾い上げることができた」と言った。
パフォーマーは自分の表現を磨くことに集中する。技術を高め、演奏のクオリティを上げ、自分のパフォーマンスを完成させる。それ自体は正しいと思う。自分との戦いだ。
でもそれが行き過ぎると、「自分が何を見せるか」だけに意識が向く。内側に向く。
一生に一回の親孝行で来た人もいれば、初めて来た人、ずっと追いかけてきた人、十年ぶりに来た人もいる。同じステージを見ていても、それぞれが持ってきた期待や文脈はまったく違う。
観客それぞれの裏側にある熱を想像し、それを汲み取ってアウトプットする。演奏技術を磨くことに集中するだけでは、たぶん不十分なんだと思う。
クリエイターにも同じ構造がある
クリエイターも同じ構造に見える。
自分の表現を磨くことに集中する。技術を高め、デザインのクオリティを上げ、自分のアウトプットを完成させる。それ自体は正しい。自分との戦いだ。でもそれが行き過ぎると、「自分が何を作るか」だけに意識が向く。内側に向く。
受託デザインにも、山口一郎さんの言う「観客」がいる。
サイトを使うユーザーだ。
ユーザーのことを考える。
それはクリエイターとして当然のことで、誰もが意識している。
でももう一つ、見落としがちな「観客」がいる。依頼してきたクライアントだ。
分業制がクライアントを見えなくした
会社員としてデザイン会社で働いていた頃、仕事は上から降ってきた。営業が取ってきた案件を、指示通りにデザインする。クライアントの顔も背景も見えない。
どういう経緯でプロジェクトが始まったのか、誰がどんな思いで依頼を決めたのか。そんなことは知る由もなかった。
ディレクターから「こういうサイトを作ってください」と言われ、要件定義書を渡され、デザインをする。それが仕事だった。自分の作る想像力をどう発揮するかだけに集中していた。なぜ見えなかったのか。構造的な問題だったと思う。
分業制の中では、クライアントとの接点は営業やディレクターが持つ。クリエイターはアウトプットに専念する。効率的ではあるけれど、依頼の背景を知る機会がない。
仮にクライアントの背景を知っていたとしても、仕事として向き合う対象は「ディレクター」だった。ディレクターが満足すれば仕事は完了する。クライアントが本当に求めているものより、ディレクターの要求に応えることが優先される。
これは個人の問題というより、システムの問題だったんだと思う。そしてその距離は、クリエイターにとって居心地がいい。
クライアントの背景や期待を知らなければ、自分の作りたいものに集中できる。技術を磨くことに専念できる。プレッシャーも少ない。
山口一郎さんが「自分のことばっか考えてた」と言ったのと同じように、当時の自分も「自分のデザインをどう完成させるか」だけに集中していた。そしてそれが問題だとは思っていなかった。
独立しても最初は同じだった
2013年にクオートワークスを立ち上げた。Webサイトの問い合わせフォームから仕事が始まるようになると、それまで見えなかったものが見えてくる。
なぜうちに依頼してきたのか。どういう経緯でサイトを見つけたのか。何度も問い合わせを書き直した痕跡が、メールの文面から伝わってくることもある。初めて会う打ち合わせで、緊張しながら話すクライアントもいる。
問い合わせから打ち合わせ、ヒアリング、提案、制作、納品まで、すべてのプロセスでクライアントと直接やり取りする。分業制の会社員時代とは違い、依頼の背景を知らずにいることができなくなった。でも最初の数年は、会社員時代の延長線上にいた。
ヒアリングで「なぜ今リニューアルするんですか?」と聞く。クライアントは答える。「デザインが古くなったので」「スマホ対応したいので」。そういう表面的な理由を聞いて、「わかりました」と進めていた。
変わり始めたのは、あるプロジェクトがきっかけだったと思う。
創業20年の中小企業のサイトリニューアル。最初のヒアリングで社長は「デザインを新しくしたい」と言った。でも話を聞いていくと、実は数ヶ月前に創業者から社長が交代していた。新社長は会社の方向性を変えたいと思っていて、そのための最初のステップとしてサイトリニューアルを考えていた。
つまり単なる「デザインのリニューアル」ではなく、「企業の転換点を支えるツール」だった。
それを理解してから、提案の内容が変わった。デザインの良し悪しだけでなく、「このデザインが新しい方向性をどう表現するか」を提案した。社長の決断を後押しする理由を、提案書に書いた。
背景を知ると仕事の質が変わる
ヒアリングの質問は次第に変わっていった。
「なぜ今なのか」「なぜうちに依頼するのか」「このプロジェクトが成功したら、何が変わるのか」。
表面的な要望の裏にある文脈を探すようになった。
ある時は、前回のリニューアルが失敗に終わった話を聞いた。制作会社とのコミュニケーションがうまくいかず、求めていたものとまったく違うサイトができあがった。
最近リニューアルしたけど全然だめなので再度デザインだけ変えたいという人もいて、担当者は社内で責任を問われた。だから今回は慎重に制作会社を選んだ。そんな人もいた。
その背景を知ると、仕事の向き合い方が変わる。
単なる「Webサイト制作」ではなく、「前回の失敗を取り戻すチャンス」に見えてくる。担当者の期待と不安に応える責任が生まれる。
だから提案も変わる。デザインの話だけでなく、プロジェクトの進め方、コミュニケーションの頻度、確認のタイミング。前回失敗した理由を踏まえて、今回はどう進めるかを丁寧に説明した。
制作中も変わる。クライアントからの修正依頼に対して、単に「わかりました」と応えるのではなく、なぜその修正が必要なのかを一緒に考える。前回の失敗を繰り返さないために、納得いくまで話し合う。
山口一郎さんがミズキの話を聞いて「命かけてやる」と言ったように、背景を理解することで妥協しない理由ができる。
別のケースでは、初めて大きな予算を投資してサイトを作る経営者がいた。何社も比較検討して、最終的にうちを選んでくれた。
その決断の重さを知ると、「期待に応えなければ」というプレッシャーではなく、「この決断を正解にしたい」というエネルギーに変わる。
提案の説得力が上がる。なぜこのデザインなのか、なぜこの構成なのか、なぜこの機能が必要なのか。経営者の投資判断を支える理由を、具体的に説明できるようになる。
これが「背景をエネルギーに変える」ということなんだと思う。
クライアントのドラマを理解することで、単なる作業ではなく、意味のある行為になっていく。
なぜ当たり前のことができないのか
「クライアントの背景を理解する」のは当たり前のことだと思う。どのデザインの教科書にも書いてある。
でもできない。なぜか。
一つは、プロフェッショナルであるがゆえの落とし穴かもしれない。
技術を磨けば磨くほど、「自分のアウトプット」に意識が向く。ポートフォリオを充実させたい。新しい表現に挑戦したい。業界で評価されたい。
それ自体は悪くない。でもそれが過度になると、クライアントの背景は「制約」に見えてくる。
「本当はもっとこうしたいのに、クライアントの要望でできない」という不満。これはクライアントの背景をエネルギーに変えられていない証拠なんじゃないか。
もう一つは、効率化の罠。
背景を深く理解するには時間がかかる。ヒアリングを重ね、文脈を読み取り、本質的な課題を見極める。効率を優先すると、このプロセスが削られる。表面的な要望を聞いて、それに応えるだけになる。
山口一郎さんが「自分のことばっか考えてた」と気づけたのは、ミズキという具体的な人間の具体的なドラマに触れたからだと思う。
抽象的に「観客のことを考えよう」と思っても、実践は難しい。
受託デザインも同じで、具体的なクライアントの具体的な背景に触れ続けることが必要なんだと思う。それを12年間続けてきた。
クライアントのドラマを知る、想像する。その背景をエネルギーに変える。
山口一郎さんの「我々だけのドキュメンタリーじゃない」という言葉。それは受託デザインにもそのまま当てはまると感じました。
制作会社側だけのプロジェクトではなく、そこには必ず依頼してくださったクライアントのドラマがある。12年間、どこか漠然と感じていたことが、サカナクションの配信を聞いてようやく言語化できました。
観客のドラマを想像するように、クライアントのドラマを想像する。その背景を表現のエネルギーに変える。 それは、当たり前のことを当たり前に実践し続けるということ。簡単に聞こえますが、構造的にも心理的にも非常に難しいことです。
多くのクリエイターは「作る想像力」を磨くことに全力を注ぎ、ポートフォリオもその成果で構成されます。しかし私は独立して12年、問い合わせから始まる一対一の仕事を通じて、「背景を想像する力」を同時に磨いてきました。 ヒアリングで何を聴き、提案書に何を書き、制作中にどう向き合うか。 それこそが自分の個性であり、クオートワークスの特徴になっているのではないか。今はそう思っています。
依頼者は、常に本気です。そこには当然プレッシャーがあります。 しかし、怖さのない仕事など、おそらく面白くはないとも思います。